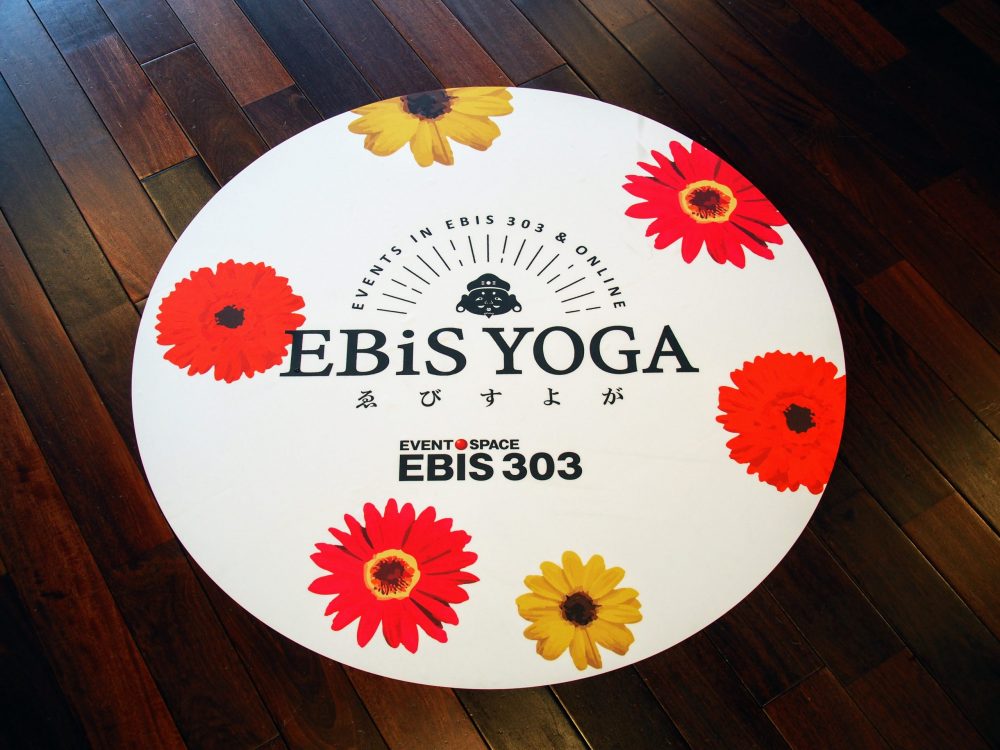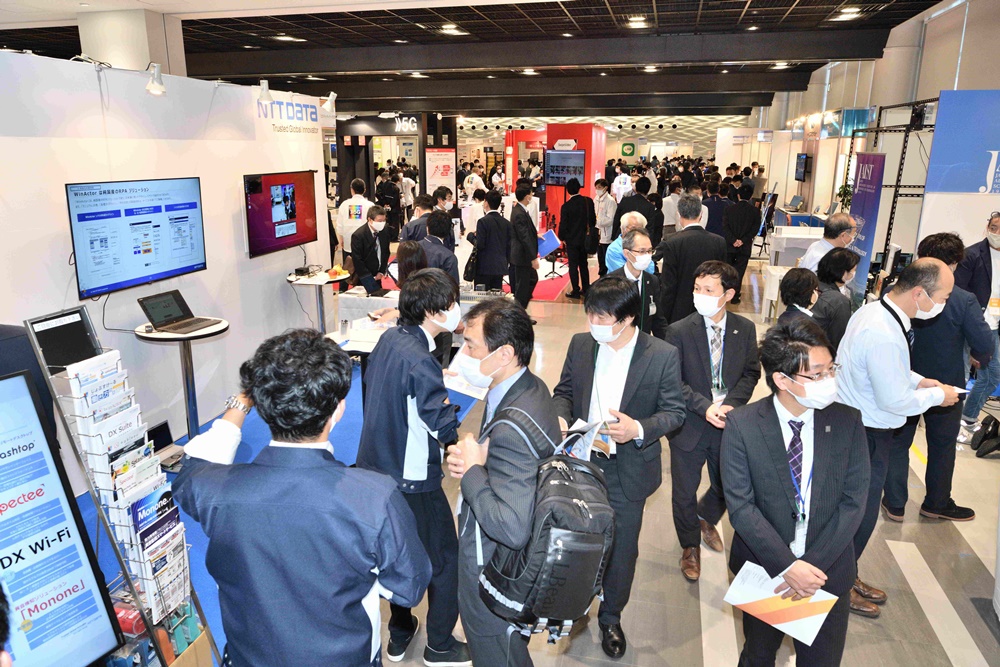<配信会場>光和本社(東京・江東区)
<配信会場>光和本社(東京・江東区)
日本映像機材レンタル協会(JVRA)はこのほど、会員同士のパネルディスカッションを実施した。コロナ禍でイベント開催のあり方が模索される中、今回のパネルディスカッションはリアルとリモートの出演者で構成。協会内でも関心が集まる①配信業務の実情、②バーチャル撮影とxR、③IPスイッチャーをテーマに各社が持論を展開した。
<出演者>
西雄基氏(光和)、石丸隆氏(シーマ)、菊地利之氏(ヒビノ)
占部吉直氏(光響社)、田上春晃氏(西日本シネ用品)、渡辺誓氏(コセキ)
新井正紀氏(シネ・フォーカス)、松原英明氏(映像センター)、原伸一氏(レイ)
増加傾向にある配信イベント
西 最近は各社さん、配信の仕事が圧倒的に増えてきたと思いますが、皆さんの近況はいかがでしょうか。
石丸 コロナ前は配信の仕事をやっていた記憶はあまりないですよね。コロナ禍で急に配信の仕事が増え、会員企業も機材をどんどん導入しています。会員の中には未だかつてないほど仕事が増えた会社もあるようです。
菊地 やはり「Zoom」や「Microsoft Teams」の力が大きかったと言えますね。
石丸 実はコロナ禍に関係なく成長市場ではありました。「YouTube」を軸にストリーミング配信は結構あったので。ただ従来のわれわれの仕事は大型映像やローカルな環境で完結していたため、あまり注力していなかったのですが、コロナ禍で加速度的に仕事が増えてきた。おそらくこれからもこのマーケットは大きくなっていくのでしょうね。
西 最近はリアルなイベントの動員数を減らして、配信も行うハイブリッド形式が選ばれることも増えました。今後はどちらかが無くなるというより、両方一緒に運用していく気がします。
顕著な世代間ギャップ
石丸 ある配信サービスの利用者属性を調べてみると、その内訳は「視聴のみ」が約60%、「配信も視聴も行う」が約30%、「配信のみ」が約10%だそうです。さらに年代別で見てみると「視聴のみ」の60%のうち、ほとんどが30代以下の若年層。逆に30代以上は、配信している割合が多いという結果が出ています。つまり情報発信する人と受け取る人が世代によってはっきり分かれていると言えます。これも日々変化していく割合ではあります。
菊地 コロナ前と後でこの業界を志望する、若い世代の「映像」の捉え方が変わってきていることは実感しています。以前はリアルライブに大きな魅力を感じて当社を志望する人が多かったのですが、いま新卒面接をする中で、配信ライブの演出における映像演出に関わりたいという若者が多くなったと感じます。しかしまさしくその通りで、コロナよるリアルライブの自粛という社会現象は結果的に、映像演出の可能性を広げたと言っていいと思います。
西 入社面接時の自己アピールになっているということですか。確かに、新しい仕事の種類が増えてきていますからね。これまでのようにハードウェアを使いこなしてお金を稼ぐだけではなく、多角的に仕事を捉えてビジネスを広げなければなりません。
 左から西氏、石丸氏、菊地氏
左から西氏、石丸氏、菊地氏
バーチャル撮影とxR
西 バーチャル配信やxR撮影スタジオについてはいかがでしょう。最近は国内外でも盛り上がっています。
菊地 AR・VR・MR・SRなどの総称がxRですが、それぞれの技術の境界線が見えなくなってきていることは、われわれの視点から見てもそう思います。また、xRは言わば「“存在しない空間”に“存在しないもの”をいかにリアルにカメラ内で表現するか」という技術なので、ある意味、突き詰めるほど地味になっていくものでもあります。自然に見える背景が実はバーチャルだったり。それを作り出すのがわれわれの仕事になってきています。
コロナ禍で配信ライブが主流になってきた頃、アーティストから「ただ配信ライブをやるだけでは面白くないので、見ごたえのある映像をつくりたい」という要望が多くありました。その経験の中で当社では、カメラトラッキングシステム「RedSpy(レッドスパイ)」がxRの演出を実施する上で重要な役割を担っています。
西 使用するカメラはどんな機種でもいいんですか。
菊地 レンズは専用のものを使用しますが、カメラは何でも構いません。ただしキャリブレーション(調整)済みのカメラで行うのが一番いいです。
西 仮設で設営するんですよね。メディアサーバー側とカメラのキャリブレーションの時間が結構必要になるのではありませんか。
菊地 当社の場合ですと、メディアサーバーは「disguise(ディスガイズ)」を使用しています。ディスガイズとレッドスパイの親和性が非常に高かったため、ディスガイズ側でキャリブレーションする事が可能です。ですので、当社のシステムではキャリブレーションは短時間で行う事ができます。
西 ところで最近、ヒビノさんは新しい撮影スタジオを開設したと聞きました。xR配信を実施する上で、何ミリピッチのLEDディスプレイを選択したのでしょうか。
菊地 当社のスタジオ「Hibino VFX Studio」は、背景として使用する撮影エリア正面のLEDディスプレイに、1.5mmピッチの「Flip Chip LED」を用いています。グリーンバックと比較してLEDディスプレイを使うことは臨場感が圧倒的に違うため、映画やドラマ撮影でも需要が高まっています。配信ライブでも視聴している人に向けたエフェクトを付加価値として提供するケースが増えています。
IPスイッチャーの展望
西 IP系スイッチャーの今後については、どのように捉えていますか。今回のパネルディスカッションでも使用している「TriCaster(トライキャスター)」のほかに各社から新製品は出てきています。
石丸 従来、我々の仕事は、比較的「密」になる要素が多いものでした。そういった視点で考えると、インターネット網を活用することで、今までと変わらないオペレーションが遠隔地からでもできるようになります。そのような環境がいずれ訪れる、のではなく、すぐ目の前にある状態と言えます。
スイッチャーにおいては、他の機械とのコネクトの仕方が今までのものと根本的に異なっているので、一度IPの世界に入って慣れてしまうとおそらく元の世界には戻れない。
各種信号の出し入れの概念を僕らも見直し、概念の取捨選択をしていかなければならないでしょう。
また、よく経験があると思いますが、展示会の現場でメディアサーバーなどの送出機器を使う際、映像コンテンツをUSBで持ってくることがありますよね。大きな容量のものを。それを普通に取り込むと時間がかかりますが、IP系のスイッチャーを使うことで、例えばコンテンツ制作会社の編集ルームとアサインできれば、直接情報を流してもらうこともできます。
西 今はまだインフラの問題があって、安定した回線を確保するのが難しいと感じています。
石丸 そうですね。ただ、インフラが整備された後になって初めてわれわれがIP系商材のアプローチをしても、結局遅れてしまう。少し使いづらくても、今のうちにトライアルしていくことが大事だと思います。クラウドとの連携はわれわれのビジネス拡大の可能性を秘めており、非常に夢のあるシステム。コロナが収束しても、高付加価値なサービスを提供していく上でIP系スイッチャーは欠かせないものであると考えています。