レイは2024年4月17日から19日の3日間、六本木 AXISギャラリーにてDigital Content Exhibition “SEED5” を開催した。
“SEED” は、アイデアの「種」になるような体験型デジタルコンテンツを紹介する内覧会。
5回目となる今年は、レイのディレクターやエンジニアが制作した7種類のコンテンツを展示。
来場者は、イベントや事業で活かせるアイデアを見つけようと、コンテンツを楽しみながら説明に耳を傾けていた。
カメラ・映像機器・PCというシンプルな構成のインスタレーション。
リアルタイムの映像の上に、数秒前の過去の映像が次々と重ね合わされていく「異なる時間の流れ」をテーマにした作品。
過去の映像に再生速度・静止・逆行など6パターンの加工が施され、現在の映像にオーバーレイされる。
作品名の「カイロス」はギリシア語で、人間の内面的な時間を表すという。
なお、半円型の映像装置にはレイが所有する湾曲可能な次世代LEDディスプレイ「RUBY」を使用している。
・空港、駅、オフィスのエントランスなど、大勢の人の往来がある場所への設置など
・大人から子供まで楽しめる間口の広さも特徴
MRデバイスを通してアートを鑑賞するコンテンツ。
はたから見ると空っぽの額縁が宙に浮かんでいるだけだが、VRヘッドセット(Meta Quest)を装着して、周囲に漂っている「単語が書かれたボール」を手で(コントローラーで)つかんで額縁の中に投げ込むと、AIがその単語を反映した画像作品を額縁の中に自動で生成する。
AIはStable Diffusionを使用。
・エンタメ系のイベント、美術館・博物館での体験型コンテンツなど
・AIを使わないパターンや、2Dではなく3Dのアートを表示するパターンも考えられる

街の映像を眺めると、視線の先にあるモノが発する音だけが(歩く音、鳥の鳴き声、車や電車の走行音、街頭ビジョンなど)拡大されて聞こえてくるコンテンツ。
視線をトラッキングできるデバイス「アイトラッカー(Tobii)」が赤外線で人の瞳孔を検知し、天井の指向性スピーカーで音を再生している。
メガネやゴーグルは必要ない。
・視線を向けた先のメンバー・キャラの声が大きく聞こえるアイドルやアニメの映像など
・野外での設置も可能
3Dメガネを装着してスクリーンを見ると立体的に見えるだけではなく、鑑賞者の頭の位置・角度に応じて映像のアングルも変化するため、壁の向こうに「もう一つの世界」が広がっているような体験ができる。
ヘッドトラッキング と プロジェクション、立体視( 3D映像)を組み合わせ、1枚の平面スクリーンで没入体験を実現した。
・本来は描かれていない部分まで見える(のぞき込める)絵画
・スポーツの試合を特殊カメラで撮影し、色々な角度から鑑賞 など
AIで生成された映像が、グネグネと動くロボットアームの姿に合わせて変化しながらスクリーンに映し出される。
アームの関節の動きを数値化してPC上で3D化、その画像とプロンプトを組み合わせて植物や石像、バレリーナなどの映像をAIで生成する。
作品名はarm「腕」と「真似る」を意味するmimicを組み合わせたもの。まるでアームの動きを真似るように、リアルタイムで映像が生成されていくのが特徴だ。
AIのモデルはStream Diffusionを使用している。
・ロボットでなく子供など人の動きを読みとってAIで映像を生成
・クラブやライブでDJの動きを読み取ってバックにAIで生成した映像を再生する など
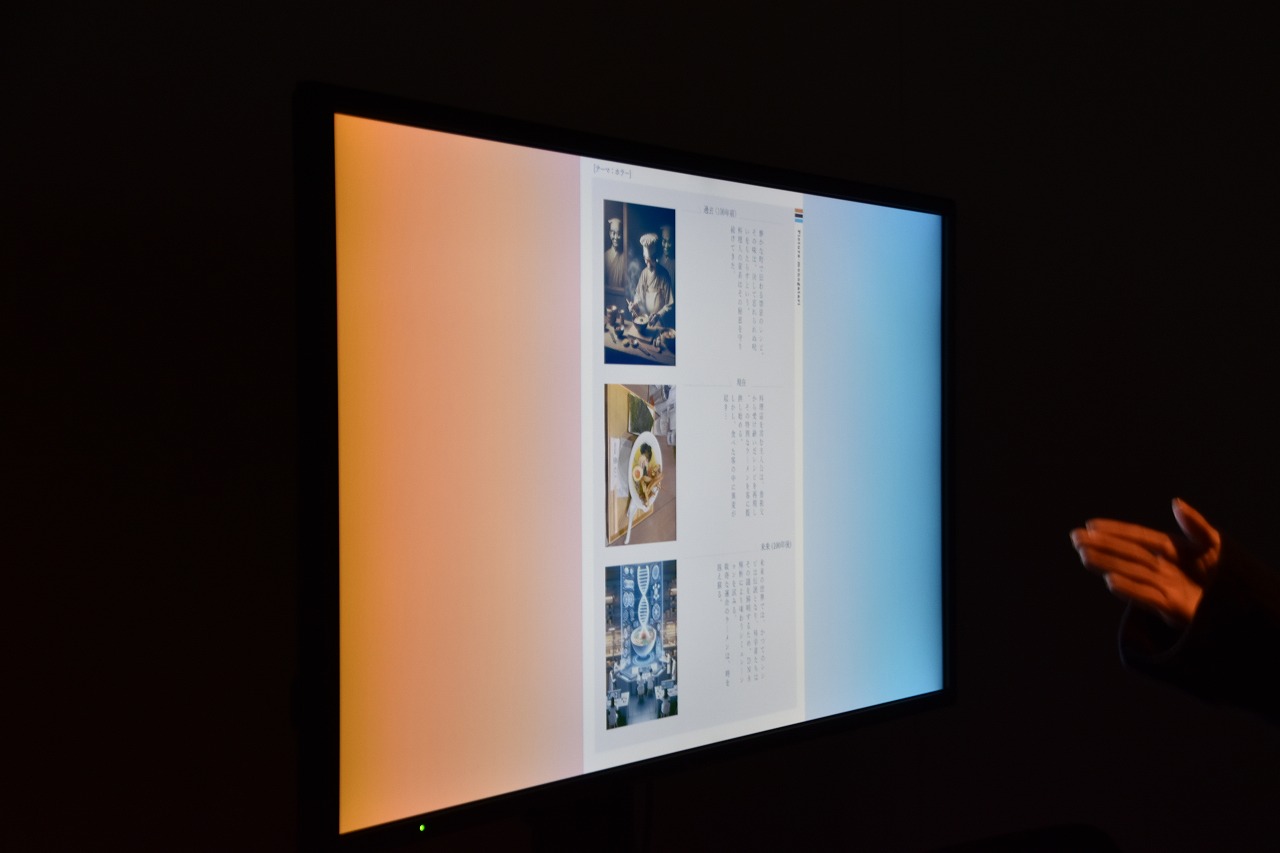
来場者がアップロードした写真から、AIがその「過去」と「未来」を創作して文章と画像を生成。
まるで3ページの絵本のように1つの「物語」を仕上げて、ポストカードに印刷してくれる。
アップロードした写真をChatGPTで分析し、Dall-E 3で「過去」と「未来」の画像を出力している。
・学習させることが可能なので、企業とのコラボなども想定できる
・コンパクトに設置できることも特徴

来場者の「脈拍」による波形から、曼荼羅(まんだら)風のデジタルアートを生み出す。
デザインモチーフは植物の「葉脈」。BPMが高まると色が赤くなり、下がると緑に変化する。
UnityとArduino、パルスセンサーなどで構成されている。
ガチャガチャと似た、何が出るのかわからないエンタメ性も特徴。
・イベントの入場時に、その人のテンションがどのくらい上がっているかを可視化する
・未来の健康診断 など
・声や温度もビジュアライズは可能であり、また別の形でのアウトプットも考えられるため、様々な応用が想定できる
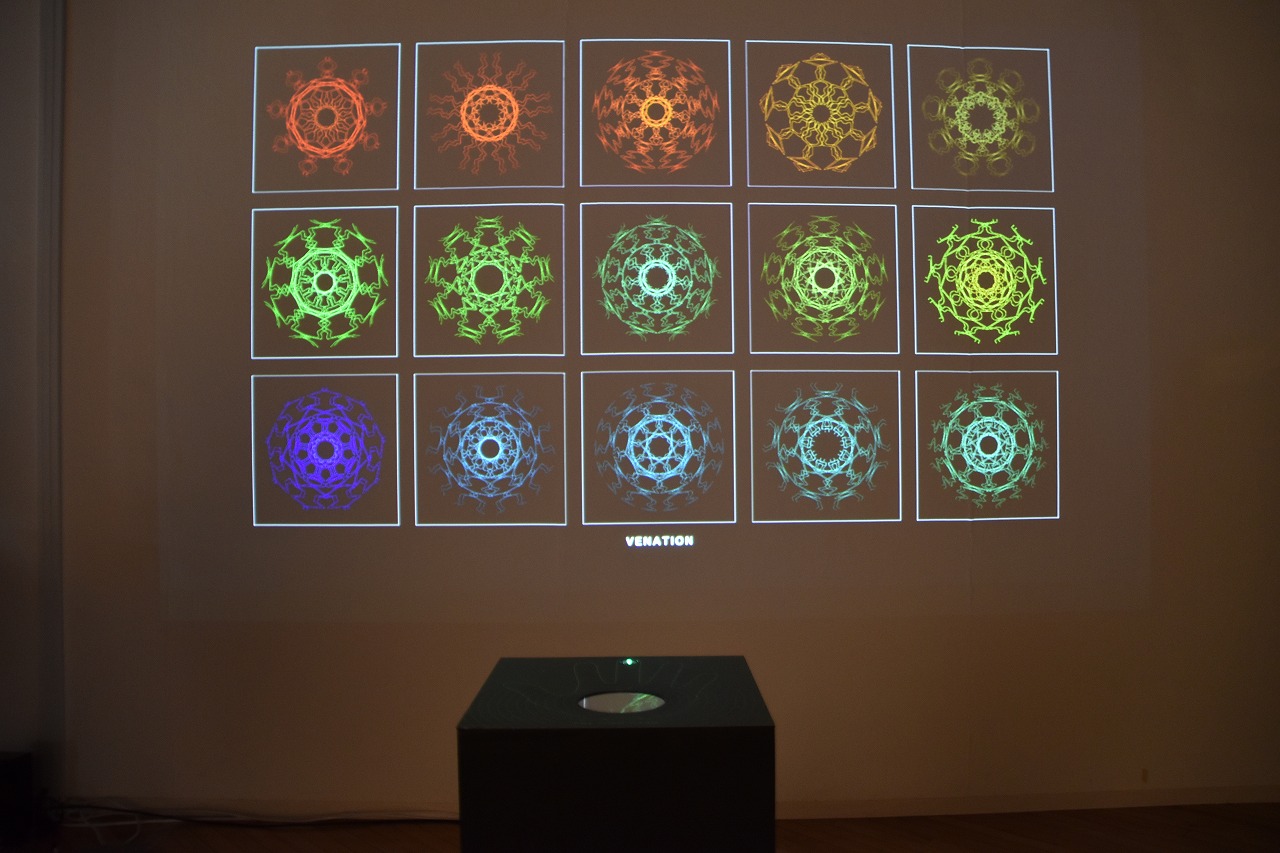
会場ではイベントの際に活用できるRayオリジナルプロダクトも紹介されていた。

来場者の自撮り動画を集めて、自動でコラージュムービーを生成するムービージェネレーター。
来場者は自分のスマホで特設Webサイトを開き、自撮り動画を撮影&アップロードするだけなので、専用アプリも必要ない。
自撮り動画はその場でムービーに反映され、イベント演出などに活用できる。
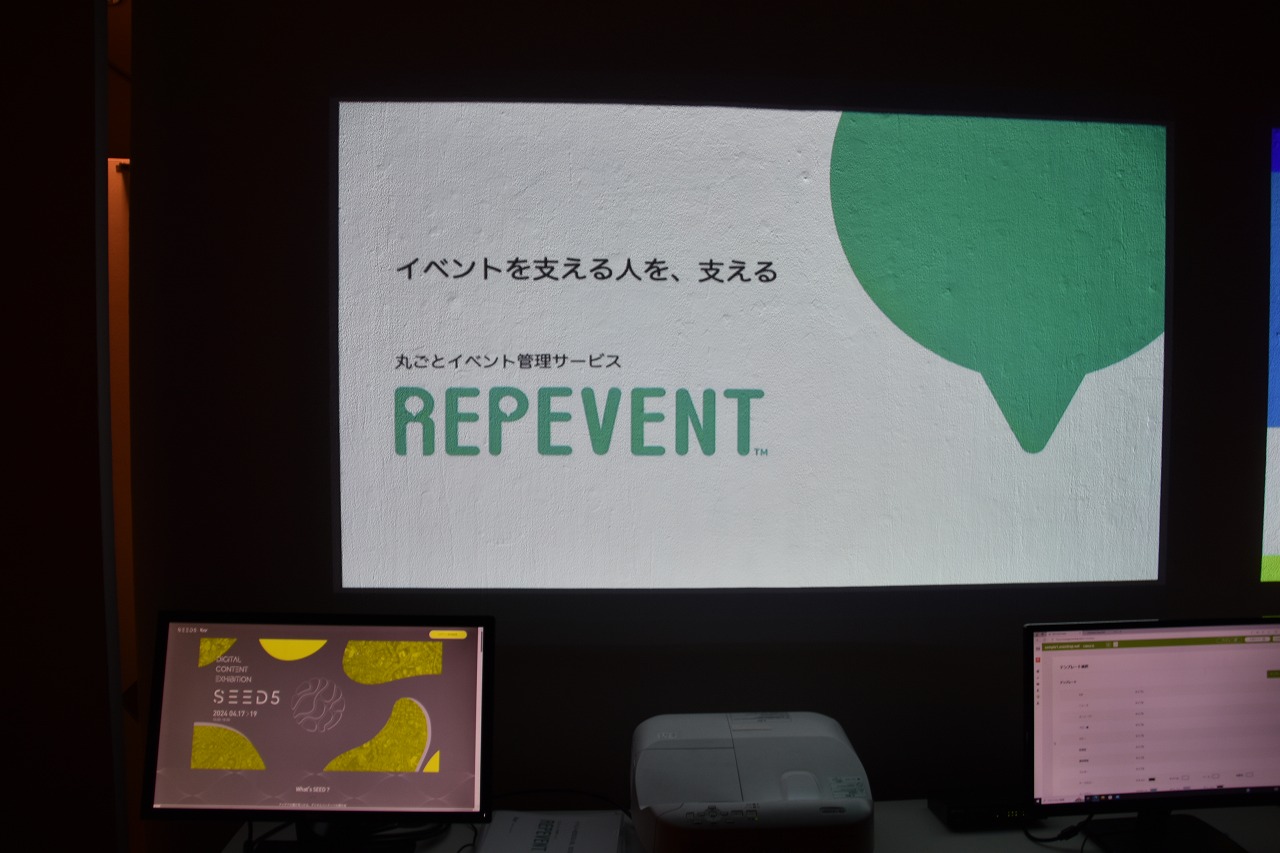
ティザーから参加申込み、オンライン視聴、フィジカルイベントでのチケット管理までカバーするイベントプラットフォーム・サービス。
イベントサイトの作成からメール送付まで一括で管理できる。
夏と秋ごとにさらにアップデートされていくという。







![[座談会]映像業界の次世代経営陣に聞く 変化する業界にいかに向き合うか/日本映像機材レンタル協会(JVRA)×ピーオーピー 合同企画](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/03/roman-skrypnyk-gjA24divsqw-unsplash-218x150.jpg)









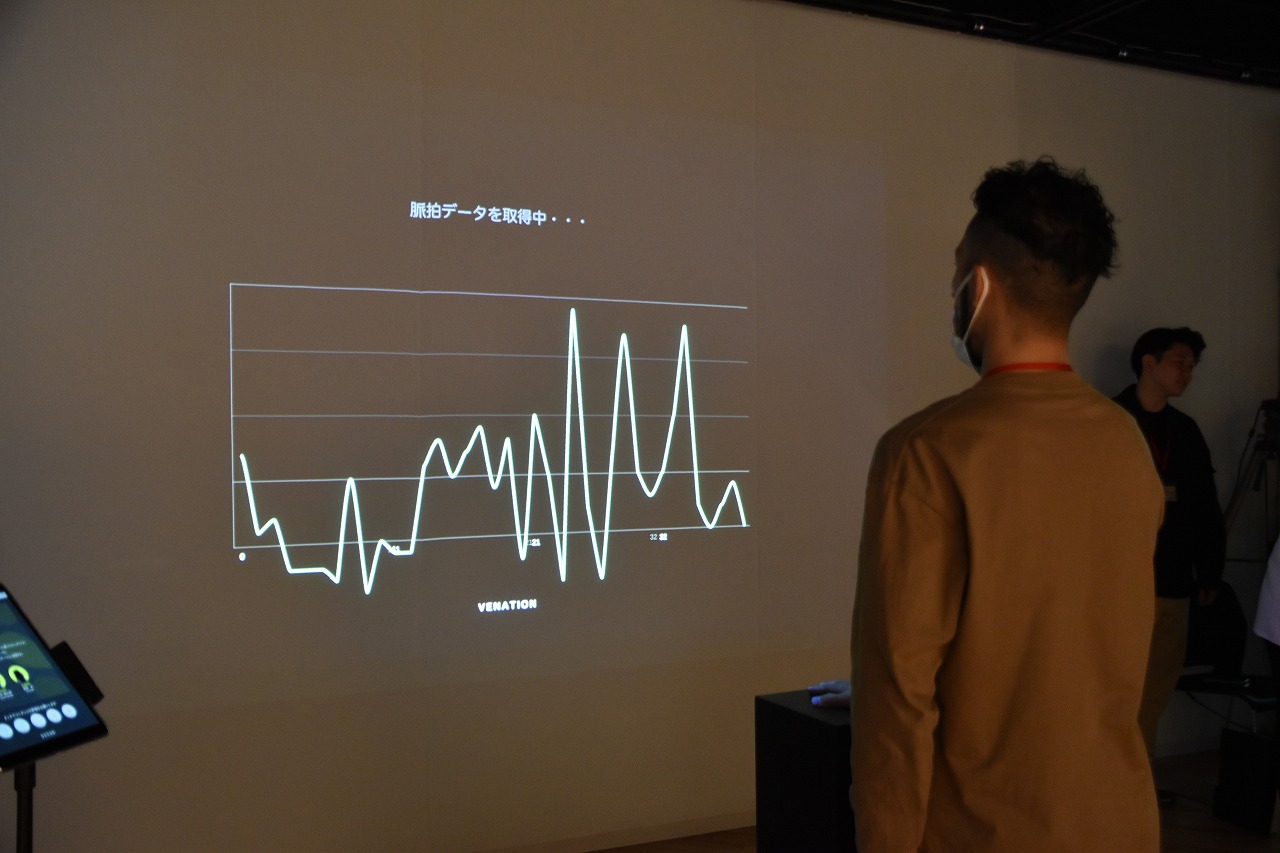
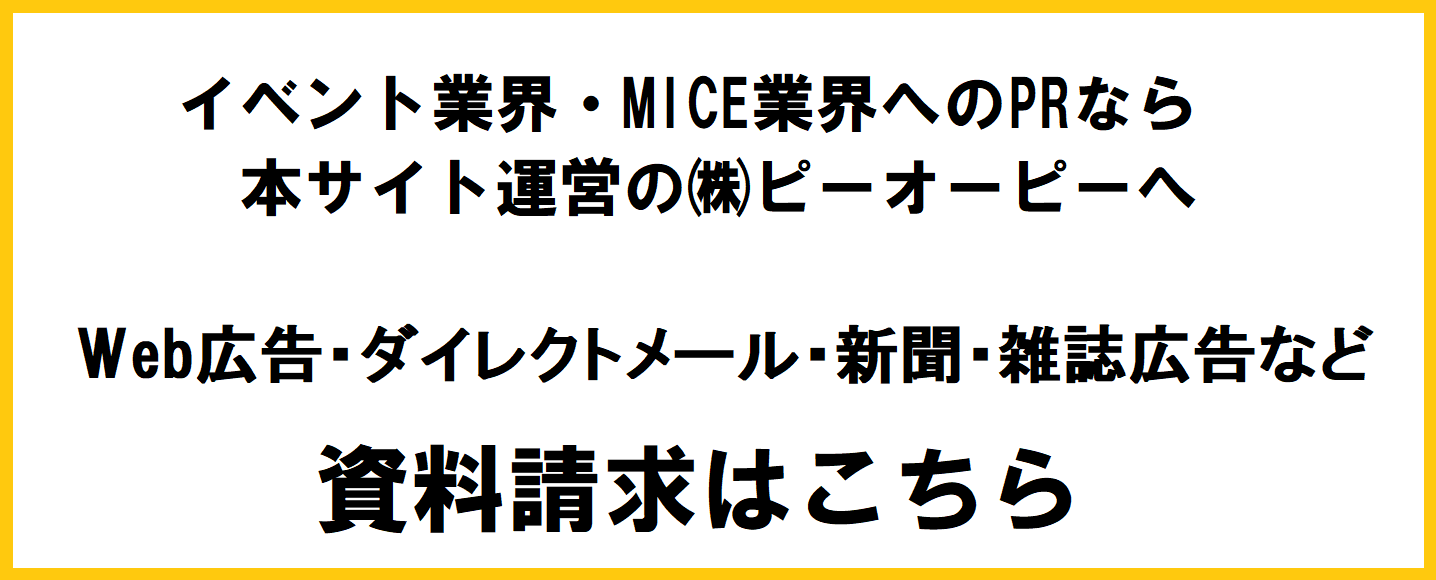



![[講演会レポート]展示会の集客力を高める工夫を解説 – 第15回 夢メッセみやぎ講演会](https://www.eventbiz.net/wp-content/uploads/2025/02/P2181115-218x150.jpg)
